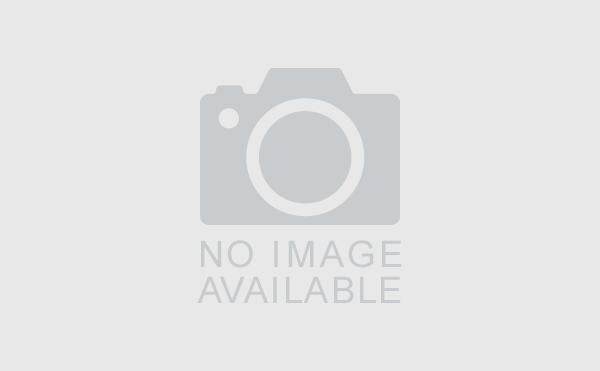ボードゲームの国際見本市 in Osaka
取引相手を見つけるは様々な方法がありますが、「見本市(商談会)への出展・来場」もその1つです。
売りたい人(貿易でいえば輸出したい人)がブースを構えて出展、買いたい人(同、輸入したい人)が会場に来場してブースを巡って商談を持ち掛ける商談の場です。
輸出したい、輸入したいという人が大勢、一ヵ所に集まるのですから、効率よく相手と出会えるとも言われます。
国際的な見本市としては、毎年ニュースで取り上げられる電子機器をテーマにした「CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)」や、航空機がテーマの「パリ・エア・ショー」、食品がテーマの「SIAL Paris」といった巨大見本市が有名です。
これらは展示総面積何十万平方メートルを誇ります(参考:東京ビッグサイトの全会場を使うと11.5万平方メートル)。
しかしその一方で、ひじょうに狭い分野を取扱うディープな見本市もあります。
昨日、大阪でそういった狭い分野の国際見本市がありましたので行ってきました。
今年で開催2回目のボードゲームをテーマにした見本市「Board Game Business Expo Japan」です。
見本市には即売(つまり物販)ありのものと、なしのものがあり、ビジネス目的のものは即売なしのものが基本ですが、本見本市はどちらかというと物販寄りです。
それでも、韓国、台湾、シンガポール、タイといったアジアの国々から出展されており、また、日本の出展者にも自分達が作ったゲームの販路を探そうとしているところがたくさんありました。
昨年はなかったのですが、今年は午前中はビジネスアワーとして、一般来場者は入れないようにしていたのも、商談目的と即買目的の人を分けたいという意図からでしょう。
なお、見本市名では「ボードゲーム」とありますが、カードゲームや会話を主体としたゲームも含む「アナログゲーム」の見本市です。
もちろん、トランプや将棋、麻雀、オセロ、人生ゲームなんかもアナログゲームで、テーブルゲームとも呼ばれます。
アナログゲームにもその内容に流行り廃りがあります。
一時、「人狼」タイプのゲームが流行りましたが(アナログゲームの分野では「正体隠匿系」と呼ばれます)、見たところ今の流行りは「マーダーミステリー系」のようです。
シナリオ(主に殺人事件)があり、参加プレイヤーが役割を割り振られてその謎を解いていく推理ゲームですが、役割の中にはまさにその犯人もありますので、推理する側と、悟られないように推理をかく乱するという駆け引きの妙を楽しむゲームです。
参加者の会話が必須ですが、集まって話をすることがタブーだったコロナ禍の頃の反動かもしれません。
ところで、最近のアナログゲームはゲーム・メカニクス(ゲームのシステムやルール、メソッド)に高度なものがたくさんあります。
その一方で、盤面、カード、マニュアルなどほとんどが印刷物で構成されますので、印刷(コピー)だけで安価に模倣されてしまいます。
では、著作権などで保護されているのでしょうか?
実はこのあたりが難しいところで、少なくとも日本の法律では、ゲーム・メカニクスは著作権の対象とならないと考えられています。
これは判例で出ているのですが、著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を対象としているのであって、ゲーム・メカニクスのような「アイデア」は対象にしていないのです。
では、特許権はというとこれも無理で、特許は「自然法則を利用するもの」が対象である一方、ゲームルールは「人為的に決められたもの」であるために対象外となるわけです。
結果として、ゲーム・メカニズムを真似しても、著作権や特許権を侵害することにはならない(今のところは)と言えます。
なお、海外ではゲーム・メカニズムについて著しく類似している場合には不正競争防止法の対象とされたことがあります。
それでも、著作権の対象にはならなかったのは、日本の考え方と同じだということなのでしょう。
もっとも、盤面やカードなどにはデザイン、装飾が施されているのが普通です。
それらの絵柄などが「表現」となるならば著作権の対象になるでしょうし、特徴的なものを意匠権登録しているのであればそれは有効です。
また、そのままコピーして販売すれば、少なくとも不正競争防止法に引っかかる可能性は十分に高いでしょう。
有名なゲームであれば商標登録されているかもしれません。
最近は日本発のアナログゲームが海外で認められるということも出てきました。
カナイセイジさんの「ラブレター」、山田空太さんの「枯山水」が好例です。
これから海外に打って出ようという方(ボードゲームデザイナー)の方は、海外向けの権利関係についても意識を持っておいたほうがいいでしょう(I)