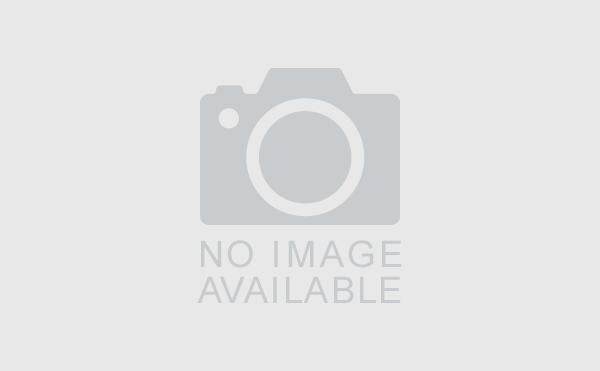飛行神社(貿易の歴史散歩)
京都府八幡市といえば、石清水八幡宮が有名ですが、そのすぐ近くに航空業界の方々から崇敬を集める神社、その名も飛行神社があります。
航空関係のお仕事に現役で携わっている方の安全祈願はもちろんのこと、CAさんやパイロットをはじめ、旅客、貨物に関わらず航空運送業界への就職を希望する方、また、業界関係資格の合格祈願をする方々などが数多く絵馬を奉納しておられます。
当社も、航空分野の資格「IATA ディプロマ(国際航空貨物取扱士)」の講座運営、講師派遣をしていますので、時折参拝しています。
1915年(大正4年)の創建、1989年(平成元年)の改装なので純和風の建物ではなく、拝殿は古代ギリシャ風、鳥居はステンレス製という変わり種ですが、祭神は天磐船に乗って降臨したという伝説により空の神とされる饒速日命となっています。
また、航空殉難者、航空業界功績者の霊も祀られています。
創建者は愛媛・八幡浜出身の二宮忠八(1866年-1936年)。
この人は英国の王立航空協会より「ライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人物」とされている人です。
ここでいう「飛行機の原理」とは「動力飛行」という意味です。
ライト兄弟が人を乗せて動力飛行機で空を飛んだのは1903年ですが、忠八は1891年に既にゴム動力による模型(カラス型飛行器)の飛行を成功させたいうのがその理由です。
残念ながら金銭的な事情で動力源の開発に難航し、世界初の有人飛行の栄誉はライト兄弟の上に輝くことになってしまったため、以後、忠八は飛行機(器)の開発から離れてしまいます。
しかし、航空機の急速な発展に伴い、航空事故が多発するようになったことに心を痛めた忠八が、事故犠牲者を慰霊するために創建したのがこの飛行神社というわけです。
この神社のユニークなところは、先に挙げたように絵馬に書かれた望みが独特なことと、飛行機型のおみくじ。
通常、社寺でひいたおみくじは、持ち帰るか境内の木の枝などにくくりつけますが、ここではおみくじを折り紙として紙(神)飛行機にし、飛ばして茅の輪をくぐらせて奉納するのです。
境内には、忠八や航空機に関する資料、奉納された航空機模型などを展示する資料館もありますので、航空業界に興味がある方は寄ってみると楽しめると思いますよ。