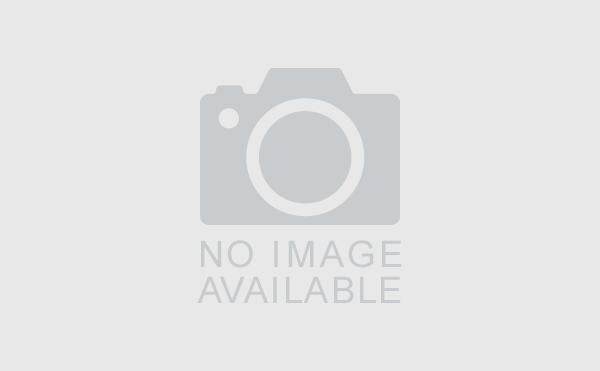また「内変機」利用の金密輸事件が
「金(金地金)」は、密輸の手口によく使われる物品のようで、税関でも「ストップ金密輸」として取り締まりを強化しています。
今年9月25日に財務省より発表された「令和6年上半期の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況」によると金地金の摘発件数は228件、押収量は約937kgとありました。
これは前年同期比で、件数では80%、量で8倍と共に大幅な増加となります。
これは、昨今の金価格の高騰が一因だと思います。
ただし、金は国際商品なので、基本的にはどの国で売買したしても相場価格になりますから、利益は売買時の相場の差でしか生まれません。
ではなぜ密輸してまで日本で売ろうとするかというと、日本の10%というまあまあ高い消費税率と仕入税額控除というシステムです。
これがなぜ密輸による利益を生むのかについては、税関ホームページに解説がありますので、御覧下さい。
偶然だと思いますが、上記の財務省発表と同じ日に、金密輸に関するニュースがありました。
「中部空港到着便で約6キロ金塊密輸試みたか 韓国籍の2人起訴」(NHK)
約6kg、課税価格で5,200万円相当の金塊を航空機を使って密輸したもので、国際線として到着した飛行機が、その後、国内線として運航されることを利用するという手口です。
これは数年前にも同種手口があった、ある意味、典型的な方法です。
・「バニラ機から大量金塊 関空便、トイレ2カ所に数十キロ」(2017年7月10日、産経新聞)
・「中部空港で金塊5キロ密輸未遂 犯行グループの巧妙トリックとは」(2018年1月30日、東スポWEB)
飛行機が国際線から国内線に変わる(これを「内変機」と言います)からといっても、乗客や貨物をそのまま載せて、というわけではありません。
旅客だと入国審査、貨物・手荷物は輸入通関、さらに検疫が必要になりますので、いったん全部降ろされることになります。
たとえ内変機の運航先に向かう人であっても、そのまま乗り続けることはできず、乗り継ぎ扱いとなるわけです。
そこで、この密輸人は「座席の下に、金塊を隠していて」、再度、同じ飛行機に乗ったときに回収しようとしていたのですが、それが発見されたというのが、この事件の顛末です。
ちなみに、ある飛行機が内変機になるかどうかは、慣れた人には「国内線の座席数」でわかるそうです。
国際線を飛ぶ飛行機は座席間のピッチが広いので座席数が少なくなります。
今はインターネット予約時にシートマップを見ることができますから、他よりも座席数が少ない便があればそれは内変機であろうと見立てを付けることができるわけです。
あとは到着や出発時刻から推測、場合によっては試し乗りをして確かめていったということだと思われます。
もちろん、内変前と内変後で同じ席を予約することが必要ですが、それも今はシートマップからできます。
この事件の記事で注目すべきは、隠された金塊を発見したのが「税関職員」だったということです。
上記の数年前の事件では、機内トイレの中に隠されていたものが発見されたのですが、発見者は乗務員であったり、掃除の方だったりでした。
それが、今回は税関職員による発見ということで、度重なる密輸手口に、税関が重点警戒していることの証左でしょう。
ところで、密輸が発見されて押収された金塊や金製品はどうなるのでしょう?
還付請求されなかったものは、密輸時点の形状に関わらず、溶かされて1kgごとのインゴット(延べ板)にされます。
そして、押収した税関が入札にかけるのですが、この条件が特殊で「一括落札」が条件となっています。
そのため、数年分をまとめて入札にかけた場合は、何億円というとんでもない金額となります。
例として、名古屋税関の2016年からの約2年分が18億円相当、東京税関の2015年から約3年分が17.5億円相当、大阪税関の2020年からの約3年分が13億円相当だったそうです。(いずれも入札時の時価)
ちなみに、落札した場合のお金は国庫に入るとことになります。(I)