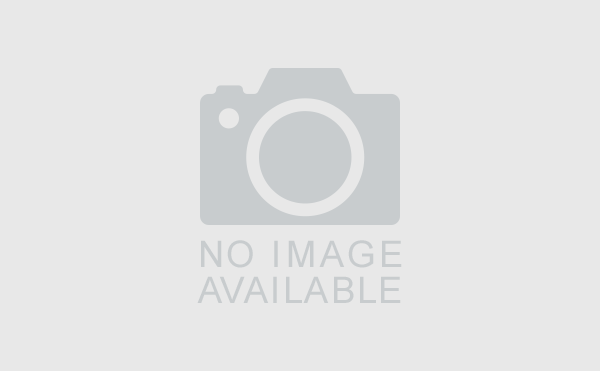電卓を使うときの注意(通関士:申告書問題)
通関士試験の通関実務科目では電卓を使うことになります。
とくに、申告書問題では按分計算や為替レートの掛け合わせなどで、掛け算、割り算を組み合わせた計算式を作って、そこに数字(金額等)を入れて電卓を叩くことになります。
その際に気をつける必要があるのが、計算結果に「99999」と続く数字が入った場合です。
例えば「0.99999」、「3.54999」、「12,999.999」みたいな感じで、小数点より上 or 下に係わらず、どの桁からでも出てくることがありえます。
結論から言えば、この場合には「最初に9が出た桁に1を足して以下を切り捨て」ることになります。
当然ながら数字が繰り上がりますので、上記の例で言えば、それぞれ「1」、「3.55」、「13,000」ということになります。
これは(いうなれば)電卓の性能限界によるもので、一般的な電卓では、「割り算で、割り切れない数字」が出た場合、ある程度の桁でそれ以下を切り捨てしまうために発生する現象です。
パソコンやスマートフォンの電卓や表計算ソフトや一部の高級電卓では発生しません。
例えば、皆さんの電卓で下の計算式を試して下さい。
① 10 ÷ 3 × 3
② 10 × 3 ÷ 3
③ 100 ÷ 3 × 3
④ 100 × 3 ÷ 3
3で割ったものに3を掛けるわけですから、普通に考えれば元の数字に戻る、つまり①は10、③は100になるかと思いきや、①は9.999・・・、③は99.999・・・となったのではないでしょうか?
また、掛け算と割り算は順番を入れ替えても構わないので、①と②、③と④は同じ結果になるかと思いきや、②は10、④は100と正しい結果になってしまうことにも注目です。
①、③は前半の割り算で割り切れない数字になったのである程度の桁で切り捨てられた(①だと3.3333、③だと33.3333)ものに3を掛けた数字になったわけです。
①と③を正しい答えにしようとするなら、上記のように「最初に9が出た桁に1を足して以下を切り捨て」ればよいというのもわかると思います。
通関士試験の輸入申告書問題では、各品目の円貨を答える必要があるわけですが、「1円未満は切り捨て」となっているので、この問題によって正誤すら変わることもありえます。
例えば、①と③でそれぞれ1未満を切り捨てして、①を9、③を99と解答してしまうと誤りになるわけです。
計算過程をどう作るか、掛け算と割り算をどちらを先にするか、計算を途中で切るか一気に計算しきるか、いずれのやり方をやっても間違っているわけではありませんが、数字が変わって正誤も変わるのは理不尽ではありますが、通関士試験はマークシート式で融通が利かないので「しょうがない」としか言いようがありません。
色々調べてみると、過去にこういう結果になった問題が出題されたこともあるようです。
しかし、ここで示した「9が続く場合は、最初に9が出た桁に1を足して以下を切り捨て」ということを覚えておけば大丈夫かと思います。
なお、最初に9が出た桁が小数点以下2位以下であれば、1未満を切り捨てでは影響ありません。