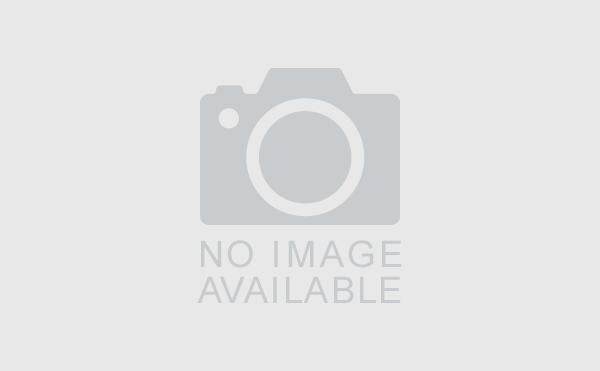検疫は英語でQuarantine
動植物の輸出入時に行われる動物検疫や植物検疫ですが、「検疫」は英語で「Quarantine」という単語になります。
国際港湾・空港で人やモノに物流に必要とされる手続きの総称であるCIQのうち「Q」はこのQuarantineのことです。
※「C」はCustoms(税関)、「I」はImmigration(出入国管理)を意味します。
このQuarantineという英単語ですが、「なんとなく英語っぽくない音だなぁ」と気になったことはありませんか?
また、カルテット(四重奏)という言葉や、立体変則四目並べゲームに「クアルト」というものがありますが、音に似た感じがあります。
そこから考えると、なんとなく「4」という数字に関連がありそうだとも思いませんか?
実はQuarantineは、イタリア語で数字の「40」を表す「Quaranta」 (クワランタ)という言葉から来ているのです。
なんとなく英語っぽくないのは、イタリア語由来だからなんです。
ではなぜ「40」なのか、その由来は14世紀に遡ります。
14世紀といえば地中海貿易でイタリア諸都市が繁栄していた時期ですが、それと同時に黒死病(いわゆるペスト)が流行した時期でもあります。
細菌やウイルスの概念がなく、当然、有効な治療法もない当時のこと、病が流入してこないようにするしかなく、入国しようとする者(海上であれば船)を入国前に隔離して、発症しないかしばらく観察するという対策がとられました。
つまり、観察期間に新たな発症者が出ていないと見極められて初めて上陸(入国)を許されたわけです。
船舶(つまり、海上貿易)における入国前の隔離・観察(要はこれが検疫です)という方策を最初に行ったのは、ラグーサという都市国家(現クロアチアのドブロフニク)と言われています。
船舶は近くにあるマルカン島(Mrkan島)やロクロム島(Otok Lokrum島)、陸路の場合はツァヴタット(Cavtat)というところで検疫を受けたそうです。
いずれもラグーサの南方にあるので、疫病は南方、つまり、当時の地中海貿易の相手ある中東・アフリカ方面から来ると思われていたのでしょう。
ラグーサはアドリア海を挟んだイタリア諸都市国家の影響を強く受けていましたが、隔離・観察という方策は、ヴェネチアにも導入されました。
ヴェネチアでは15世紀には隔離に加えて治療も行うという名目でラザレット・ヴェッキオ、ラザレット・ヌオヴォの2島が検疫島として設定されました。
ヴェネチアでのこういった検疫の仕組みが長く続き、18世紀終盤にも「検問島ラッザレット・ヌォーヴォ」(フランチェスコ・ティローニ)という絵画が描かれています。
その検疫にかけた期間ですが、ラグーサでは30日とされていましたが、ヴェネチアでは当初は30日だったものが、その後40日とされ、それが定着しました。
そう、これがQuarantineの語源が「40」である理由なわけです。
ヴェネチアは地中海貿易の雄でしたので、検疫の手法とともに、言葉も伝播していったのでしょう。
なぜ40日とされたのかについては諸説あります。
ラグーサでの隔離期間であった30日では不足だったという説もあれば、キリスト教圏では40が聖なるマジックナンバー」であったためという説もあります。
(旧約聖書でノアの箱舟の洪水が続いたのが40日であったり、新約聖書でイエスが荒野で修行をしたのが40日であったなど。)
当時の教会の影響力を考えると、キリスト教からと考える方が自然かもしれません。
こういった「島で隔離」という検疫手法は昔の話かと思いきやそうでもありません。
先般の新型コロナ禍の初期において、外国からの入国前に一定期間、島など孤立した場所で隔離した国がいくつもありました。
日本でも最初期の客船ダイアモンド・プリンセス号での隔離ということをしていましたね。
未知の病原体に対しては、隔離と観察という検疫手法は今でも有効なのです。
ちなみに「検疫」という日本語は、江戸幕府の洋書調所というところが「Quarantine」の日本語訳として当てたものです。
今では中国や韓国でも(字は違うにしても)使われています。(I)