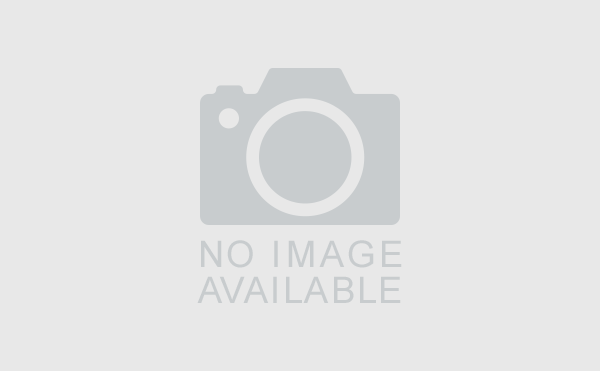外為法:輸出の許可が不要な場合(1)
通関士試験では、外為法に関する問題が例年2題出題されています。
複数選択(2点)が1題、択一式(1点)が1題という組み合わせが多くなっています。
問題内容のバリエーションがあまり多くないので、確実に3点取れるチャンス問題と言えます。
出題内容で多いのが、輸出の許可や承認、輸入の承認が不要になる場合ですが、よく聞くのが「輸出の許可が不要になる特例が覚えにくい」というものです。
これは、輸出貿易管理令別表第1の内容を、項番号だけで特例の対象となるかどうか覚えようとするためです。
そういう単純な数字で覚えようとするよりも、ザクっとした対象分野を覚えた方がむしろ楽なのです。
※これは、STC試験でも同様です。
まず1項~15項がリスト規制、16項がキャッチオール規制だというのは基本として覚えていると思います。
ここでまず1つ重要なのが、「輸出の許可が不要になる特例」はリスト規制に対してだけで、キャッチオール規制にはないということです。
これは通関士試験よりもSTC試験での方がよく出題されるテーマかもしれません。
次に、リスト規制の各項を下のとおりザクっと分類します。
・1項:武器・兵器そのもの
・2項~4項:大量破壊兵器関連の汎用品
・5項~15項:通常兵器関連の汎用品
です。
うち、「通常兵器関連の汎用品」については、
・14項:軍需品
・15項:武器・兵器への転用が容易な機微品目
として、5~13項までとはちょっと違う要注意品目扱いになっています。
これを踏まえた上で、輸出の許可が不要になる特例を考えるとわかりやすくなります。
まず、1項の「武器・兵器そのもの」は「いかなる場合も特例の対象にならない」ことが重要です。
ちなみに、この項には競技用や狩猟用の銃も含まれます。
特例で出題される代表的なものは、仮陸揚貨物、無償特例、少額特例の3つです。
仮陸揚貨物、無償特例は1項の「武器・兵器そのもの」以外であれば対象になります。
※仮陸揚貨物にはもう少し細かい点があるのですが、それは別の機会に説明します。
一方、少額特例は対象が5項~13項、15項です。
これを内容で見ると、「武器・兵器そのもの」、「大量破壊兵器関連」、「軍需品」が除かれているということがわかるでしょう。
さらに少額扱いとなる金額を見ますと、通常は100万円以下であるものが、15項+αは5万円となっています。
これは15項が「武器・兵器への転用が容易な機微品目」であることからと考えるといいでしょう。
+αとは15項も含めて別表第3の3「告示貨物」ということになりますが、いずれもその具体的な品目までは通関士試験はもちろん、STC試験でも出題されませんのでご安心下さい。
あとは、対象国によるものですが、それはまた別の機会に説明しましょう。
なお、試験問題に「上欄」「中欄」「下欄」という言葉が登場します。
これは法令というのは基本的に「縦書き」であるが故の表現です。
ウェブなどで見るとわかりにくいのですが、別表も縦書きになっています。
「上欄」とは項番号が書かれている欄、「中欄」は対象品目が書かれている欄、「下欄」は対象地域が書かれている欄です。
ここそのものが論点になる問題が出題されることはないので、あまり気にしていない人がほとんどだと思いますが、こういった点を知っているとより理解が深まると思います。