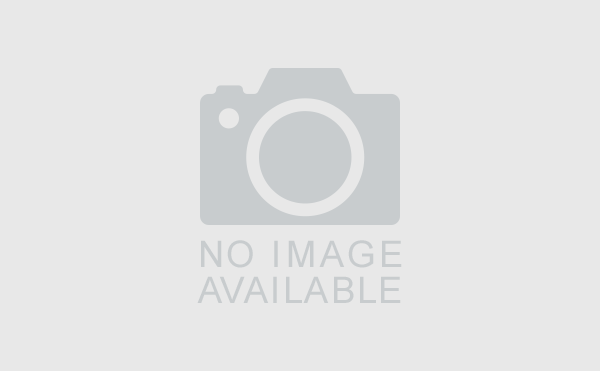外為法:輸出の許可が不要な場合(2)
前回、「『輸出の許可が不要になる特例』はリスト規制に対してだけで、キャッチオール規制にはない」と書きました。
私が行う通関士や輸出管理(STC)の講義でもこのとおり説明するのですが、よく質問をもらうのが「仮陸揚貨物や少額特例で、『やっぱり許可が必要』となるものを見たら、キャッチオール規制の内容になってませんか?」ということです。
たしかに条文を見るとそのように見えます。
具体的に見てみましょう。
まず、仮陸揚貨物ですが、下の場合には許可が必要になります。
(A)大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
(B)大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
また、少額特例についても、下の場合には許可が必要になります。
・懸念国以外の国連武器禁輸国・地域向け
(A)大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
(B)大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
(C)通常兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
(D)通常兵器の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
・懸念国、国連武器禁輸国・地域、グループA以外の国・地域向け(要は一般国)
(A)大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
(B)大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
(D)通常兵器の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ここで上げている(A)~(D)はそれぞれキャッチオール規制の規定ではこう呼ばれる内容に相当します。
(A)大量破壊兵器・客観要件
(B)大量破壊兵器・インフォーム要件
(C)通常兵器・客観要件
(D)通常兵器・インフォーム要件
このように示されているので、あたかもキャッチオール規制の対象にも、輸出許可が不要になる特例が適用されるかのように見えます。
しかしそうではなく、あくまでもこれらはキャッチオール規制の内容を流用しているだけなのです。
つまり、リスト規制品で特例によって許可取得が不要になる場合であっても、キャッチオール規制でも輸出許可が求められる状況であるならば、特例が適用されないという意味なんですね。
流れとしてはこう考えて下さい。
〇STEP1 該非判定でリスト規制品に該当 →(NO)キャッチオール規制に該当するか判断(取引審査)をする
↓(YES)
〇STEP2 輸出許可が不要になる特例に該当 →(NO)輸出許可の取得が必要
↓(YES)
〇STEP3 特例の適用除外になる場合(上記のように(A)~(D)にあてはまる等)に該当しない →(NO)輸出許可の取得が必要
↓(YES)
〇STEP4 輸出許可が取得は不要
見てのとおり、キャッチオール規制に該当する場合はSTEP1の段階で枝分かれしていますので、特例に該当するかどうかを気にしなくていいわけです。
これは、キャッチオール規制の内容が輸出貿易管理令別表16項まるごとで、他の特例とは分けて、許可が不要な場合に挙げられていることで示されています。
なお、輸出管理に関して覚えておいた方がよい別表の番号は下のとおりです。
・別表第1:輸出の許可を要する物品
・(別表第2:輸出の承認を要する物品)
・別表第3:グループA対象国(旧 ホワイト国。現在、27ヵ国指定)
・別表第3の2:国連武器禁輸国・地域(現在、10ヵ国指定)
・別表第3の3:告示貨物(少額特例の対象額が5万円以下になっているもの)
・別表第4:懸念国(イラン、イラク、北朝鮮。無償特例の一部や少額特例は適用不可)
少額特例部分はややこしいので表を示せばわかりやすいかもしれませんが、ここではあえて示しません。
皆さんでうまく表を作って見ることで整理できますので、本番試験でも怖くなくなります。