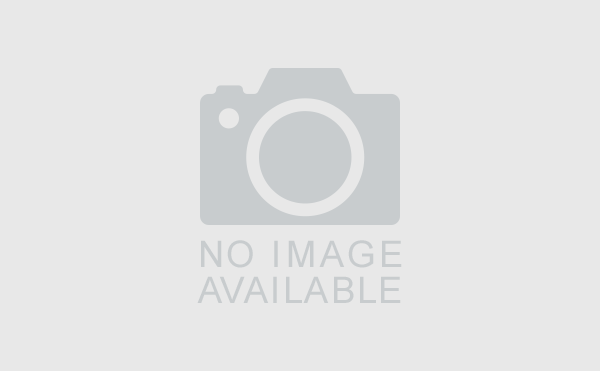続・問題文は良く読むべし!(通関士:申告書問題)
今年の通関士試験も本番が近づき、スクール各社の模擬試験も実施されています。
受験された方で「しまったー!」という声を聞くのが、申告書問題における「少額品目の解答順、解答方法」です。
意外と過去問、または、古い問題集を一生懸命解いてきた方がそうなってしまったみたいです。
法令変更があるために古いものが使えない法令問題と違い、申告書問題を含めた通関実務は、基本的に変わりません。
そのため、先輩から譲ってもらったり、古書店やフリマで手に入れた問題集で勉強する人もけっこうおられるようで、そういう人が引っかかっているようです。
間違いポイントの1つ目が「少額品目(1品目20万円以下の品目)の解答順」です。
これは以前に書いた(2023年12月「問題文は良く読むべし!(申告書問題)」)のですが、最近の問題では、解答順は「金額が多い順」で、少額品目が複数ある場合はその合計金額で見ます。
当然、合計された少額品目の金額が大額品目のいずれかより大きい場合には、解答欄では少額品目が上位になります。
しかし平成の頃は、少額品目はそうでない品目(大額品目)を金額の多い順に答えた後(つまり、1欄から4欄の後)の5欄に解答するようになっていました。
そのため、以前の解答方法に慣れてしまった方が、5欄を少額品目にしてしまって間違っている例です。
ここでは、少額品目が1つしかない場合に10桁目を「X」とするのか「E」とするのかというポイントもあります。
いずれも問題文に指示されていますので、「いつもそうだから」と読み飛ばさずに、きっちりと読むことが重要です。
平成以前の解答方式に戻らないとは限りませんので。
2つ目が「少額品目を有税品と無税品に分ける場合の解答順」です。
「有税品は税率が一番高いもの、無税品は金額が一番多いものを代表番号として10桁目をXとする」のはいいとして、解答順は「金額順」なのか「有税品が上」なのかをちゃんと見なければいけません。
3つ目が(そして、これが一番難儀なのですが)、少額品目が1つしかない場合の扱いです。
上述のように「10桁目をEとする」という指示がある場合はいいのですが、そういう指示がないこともあります。
以前は「E」の指示がないなら、むしろ「少額品目は0か複数ある」というヒントになったのですが、今はそうでもないのが困りものです。
この例でかなり凶悪な問題が第49回(2015年)の輸入申告書で出題されました。
この問題では、金額が米ドルと豪ドルの2つで示され、どっちのレートで円換算するのかということだけでも難問(スクールの解答速報でも見解が分かれた)でしたが、さらに解答順、解答方法にも罠があった問題です。
問題文の中でポイントとなる部分を抜粋します。
———-
2 品目番号が異なるものであっても、関税割当ての対象物品以外のものについては、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にまとめる。
なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。
⑴ 有税である品目については、一欄にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
⑵ 無税である品目については、一欄にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。
4 品目番号欄(⒜~⒠)には、上記2によりまとめたもの以外については、申告価格の大きいものから順に入力するものとし、上記2によりまとめたものについては、これら以外のものを入力した後に入力するものとし、当該まとめたものが二欄以上となる場合には、そのまとめたものの合計額の大きいものから順に入力するものとする。
———-
まず、2より「関税割当て品目は20万円以下であっても少額品目扱いにしない」ということを読み取る必要があります。
次に、4より「少額品目は大額品目の後にする(以前の形式ですね)」のはいいのですが、この場合に関税割り当て品目が20万円以下だとどうするのかについては、2の指示がありますので、少額品目よりも上の解答欄ということになります。
ここまではまだいいでしょう。
この問題で凶悪だったのが、有税品の少額品目が1つしかなかったことです。
2をさらっと読んでしまうと「ああ、有税品も10桁目はXにするんだな」と思ってしまいます。
しかし(1)をよく見ると「一欄にまとめた品目のうち」とあります。
「1品しかない=まとめていない」わけなので、この指示は2品以上ある場合ということになります。
1品しかない場合はこの指示に該当しないので、10桁目は関税率表にある10桁目の数字を普通に使うこということになります。
ただ、この指示だと「1品だけの場合は除外」と「1品だけの場合も含めた汎用的な指示」のどちらにも解釈することができます。
10桁目が数字とXの両方が選択肢にあったのが余計に悩ましい問題でしたが、模範解答では前者で解釈することとなっています。
このあたりは、出題者の意向がジャスティスなのでしょうがないですね。
最近の通関士試験では、申告書問題の難易度が下がっていると言われます。
品目分類が難しければ金額調整が易しい、品目分類が易しければ金額調整が難しいという感じで、解答に費やす時間が一定になるように調整されていると目されています。
その分、解答方法に罠があるかもしれません。
問題文は良く読む必要があるということですね。